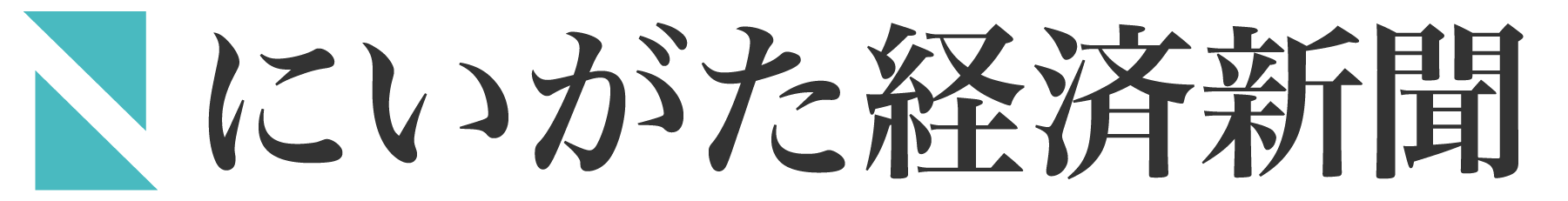99%の人に喜ばれる新潟のお土産9選!地元民が自信をもっておすすめ!
新潟のお土産を家族や職場の人に買って帰りたい。だが、どんなものを渡せば喜んでもらえるのだろう?
新潟といえば、真っ先に思いつくのが、酒や米だろう。だが、お土産となると、酒は好き嫌いがある。米もだんだんと食べられなくなっているし、何といっても、お土産としては重過ぎる。「何か新潟のいいお土産(食べ物)はないの?」。こんなことに悩んでいる人に、地元民が「絶対に喜ばれる土産」を厳選して集めてみた。
今回紹介するお土産
1.「浪花屋の柿の種」
「たーね、たーね、柿の種、元祖、浪花屋の柿の種」。このCMに代表されるように、柿の種の元祖といえば、浪花屋製菓。創業は大正12(1922)年。大阪の職人から、もち米を使ったあられの製造を学んだことが屋号の由来とされる。


浪花屋の柿の種
柿の種の始まりについて、元祖をうたう同社のパッケージにこう書いてある。
〈当時はすべて手作業で薄くスライスした餅を何枚かに重ね、小判型の金型で切り抜いて作っていました。ある日、その金型をうっかり踏み潰してしまい、元に直らずそのまま使用したら、歪んだ小判型のあられになってしまいました。
そんなあられを持って商いをしていたところ、ある主人が《こんな歪んだ小判型はない。形は柿の種に似ている》といわれ、そのヒントから大正13年『柿の種』が誕生しました〉
金型を踏み潰したのが、浪花屋の創業者である今井與三郎の妻だった。以来、柿の種は、食べたら止まらないポピュラーなお菓子として定着していった。
同社のホームページによると、生姜醤油ラーメンの元祖「青島食堂」との新潟限定コラボ商品のほか、わさび味、青じそ風味などがある。また、花火王国新潟をイメージした化粧缶入りなどパッケージが特徴の商品も揃えている。
2.「サラダホープ」
〈ある日、一通の封書が本社に届いた。差出人は女性。今までにないおいしさです、という賞賛のファンレター。たった一通ではあるが、稀有なことには違いない。そしてこの話、まだ続きがある。それは封書の宛先。亀田製菓ではなく“サラダホープ本舗様”になっていた。よく届いたものだと感心する一方で、商品は好調、爆発的に売れても亀田製菓の知名度は当時まだまだ低かったのだなと、そんな思いもする〉


サラダホープ
米菓トップの亀田製菓は昭和21(1946)年の創業。同社の創業者は故古泉榮治氏で、前身は“貝塚のアメ屋”と呼ばれた亀田町農産加工農業協同組合だった。
創業家は経営の第一線から退いているものの、「製菓展道立己」という亀田製菓の社是はそのままだ。冒頭は昭和62(1987)年に刊行された同社の30年史、『製菓展道三十年』の一節。当時、同社の会長は創業者の古泉榮治氏、その息子である肇氏が社長に就任して4年経過した頃だった。売上高は現在の半分ほど、約520億円だった。
冒頭は現在も亀田製菓の看板商品の一つとなっている「サラダホープ」が売り出された頃、昭和36(1961)年当時の逸話だ。サラダホープのように、米菓を含む菓子業界で半世紀以上ものロングセラーを続ける商品はごくまれだ。
亀田製菓の定番といえば、ピーナッツ入りの柿の種だが、こちらはサラダホープの数年後、昭和40年代に入ってから急速に売り上げを伸ばした。柿の種と共に、現在同社の看板商品となっているのがハッピーターン。こちらが登場したのは昭和51(1976)年。これらが登場する前の同社にとって、サラダホープは〈特大ホームラン〉(『30年史』)とも言うべき大ヒット商品だった。
柿の種と同様、サラダホープはもち米ベースのあられの一種。いわば「油かけあられ」で、スナック風、洋風に仕上げるためにサラダ油が使われ、調味料が工夫された。基本は塩味のサラダホープだが、表面を油でコーティングすることで、塩が落ちにくくなっている。
ただし塩だけでサラダホープの奥深い味わいは出せるものではない。その秘密は調味料にあった。『30年史』によれば、たまたま開発者の眼前にあったマヨネーズがヒントになり、あのサラダホープのまろやかな味が誕生したという。
〈洋風化市場の中でスクスクとヒット商品に育ってくれヨ〉といった願いからサラダホープと名付けられた。洋風、横書きのネーミングは業界初だったという。〈新潟の地元で先発して売り出したサラダホープ、これが大ヒット。生産が追い付かず、県外に供給できない。(昭和)37年ぐらいに県外に出した時には、県外のメーカーが競って同じような商品を出しており、ウチが後発になっていた〉(『30年史』)
中には「サラダトップ」などという商品も出回っていたという。この昭和30年代の大ヒット商品が、続く昭和40年代のメガヒットを誘発することになった。それが亀田製菓の定番で、今日も人気の「サラダうす焼き」だ。
〈その開発コンセプトは、ひとことでいえば洋風スナック嗜好に応えようというもの、そしてまたコカコーラなどのドリンクにもよく似合う、そんな〟軽さ〝を持った米菓ということになる。お判りのように、これは例の〟サラダホープ〝の延長線上に位置する製品でもあった〉(『30年史』)
新潟のご当地グルメでもあるサラダホープだが、米菓業界を一変させてホープでもあった。
3.「浮き星」

浮き星
新潟市中央区の上古町商店街に、店舗と作業場を構え、Tシャツや雑貨などを中心にデザイン・製作するヒッコリースリートラベラーズの「浮き星」。明治33年創業の「明治屋」(新潟市)が作っている新潟銘菓「ゆか里(ゆかり)」(あられに砂糖蜜をかけた新潟の伝統的菓子)を、ヒッコリーが新たにデザインしたパッケージに入れた菓子だ。そのまま食べるほか、お湯に浮かべて溶かして食べる。価格は380円から。
かつて『新潟名物といえば、ゆか里』と言われたほどだったが、ヒッコリーが、ゆか里と出会った当時は、明治屋だけが製造していて、後継者もいなかった。まさに風前の灯といった状況だったが、今では菓子そのものの魅力に加え、お洒落なパッケージが人気を呼び、北海道から沖縄まで全国数百か所に卸すまでになっているという。また業・施設のロゴを入れた缶入りの浮き星を販売する取り組みなども行っている。
新しい新潟の定番のお土産といえる。
4.「たなべのかりん糖」

たなべのかりん糖
本県の米菓出荷額は全国シェアの56・4%(2014年)と圧倒的だ。米菓メーカーのビッグスリーは、亀田製菓、三幸製菓、岩塚製菓。
こうしたメーカーで看板商品の一つになっているのが「柿の種」だ。大手メーカーで大量生産される「柿の種」は、本県の米菓を代表する人気ブランドになっている。
この「柿の種」の対局に位置するヒット商品がある。それが「たなべのかりん糖」だ。加茂市にある老舗、田辺菓子舗が製造・販売している。長さ10cmほどとデカく、刀のような形をしている。かりん糖ながら、歯ごたえはさっくりとしていて、しっとりと柔らかい。自然な甘さで、優しい風味だ。
十数年前、「週刊文春」で紹介され、反響を呼んだ。東京・原宿にある県のアンテナショップ「表参道・新潟館ネスパス」では常に売れ筋の一つになっているという。ただし「柿の種」のように、スーパーやコンビニで買えるわけではない。
かりん糖は主な原料が小麦粉で、水や砂糖などを加えて生地をつくる。カットした生地を油で揚げ、黒砂糖などの蜜をからめ、乾燥させて完成だ。「たなべのかりん糖」は完全手づくりで、製造マニュアルもない。天ぷら鍋で揚げるのも天ぷら鍋を使い1本ずつ揚げるのだという。そのため生産量に限界があり、ネット販売のほか販売店は極めて限られている。
平成27年5月、昭和2(1927)年創業の田辺菓子舗は、その株式を岩塚製菓(長岡市)に譲渡し、同社の子会社になった。田辺菓子舗の後継者難からのことだった。岩塚製菓のニュースリリースにはこうあった。
〈瑞花をはじめとした当社グループの『原料へのこだわり』『ものづくりへのこだわり』に共感し、当社へ株式譲渡の上、当社グループの一員として事業を拡大して欲しい旨の申し入れが(田辺菓子舗から)ありました。
当社といたしましても、『たなべのかりん糖』は有名ブランドであること、『原料・品質へのこだわり』は当社のものづくりと融合できること、そしてまさに中期経営計画の『新しい価値創造への挑戦』実現の第一弾に繋がることから、株式取得につきまして決議いたしました〉
5.「瑞花」


瑞花
「瑞花」は贈答用など、高級ブランドの米菓を扱う岩塚製菓の子会社だ。長岡市や新潟市のほか、東京・銀座にも直営店がある。余談だが、今や中国の一部でもこの高級ブランドが好まれているという。「瑞花」が扱う米菓の中には、「たなべのかりん糖」のように、手づくりの工程を一部含む商品もある。
前出、県内米菓メーカー・ビッグスリーでも、原材料へのこだわりは岩塚製菓が図抜けている。同社の全商品は「国産米100%使用」だ。こうした原材料や品質へのこだわりは、手づくりを貫きとおす「たなべのかりん糖」と共通するように思われる。
6.「かんずり」

かんずり
新潟県妙高市(旧新井市)に古くからつたわる「かんずり」は、唐辛子を雪にさらした後、糀・柚子・塩を混ぜて3年間熟成発酵させた添加物・保存料不使用の自然発酵食品。まろやかな辛味と糀の旨み、柚子の香りが特徴で、四季を通じて料理の味を引き立てる。大寒にあたる日に毎年、このかんずりの製造工程の一つである「雪さらし」が、製造元である有限会社かんずり本社から徒歩5分のところにある田んぼで行われている。
かんずりは完成するまでに長い歳月を要する。まず自社や契約農家で栽培した「かんずり用唐辛子」を収穫・選別し、天然海水塩で塩漬けにする。その後、大寒の日から3~4日ほど雪さらしをする。さらに、その後、糀、柚子、食塩を加え、3年間ほどかけて、熟成・醗酵させていくのだ。
炒め物、焼き魚、鍋物、野菜炒めなど様々な料理の味を引き立ててくれる。
一方、かんずり関連商品として2018年春、東ハトから10年間熟成発酵させた香辛調味料「ハバネロかんずり」を生地に練り込んだ「暴君ハバネロ・熟ハバ」が発売された。さらに2019年1月には明星食品株式会社から、どんぶり型カップめん「明星 チャルメラどんぶり 新潟かんずり 旨辛みそラーメン」が全国販売となり話題になっている。
7.「みかづき イタリアン」
「イタリアン、ポッポ焼き、のっぺに、ラーメン♪」。ある新潟の曲の歌詞には、こんな感じで新潟のグルメが登場するが、トップに出てくるイタリアンも人気のお土産だ。

みかづき イタリアン

小国製麺の冷凍のイタリアン
名前はイタリアンだが、実際は、「洋風ソースかけ焼きそば」。原材料は、焼きそばのような太めの中華麺。この麺とキャベツ、もやしなどを炒め、ソースなどで味付けしている。ソースはトマトソースのほか、カレーソース、ホワイトソース、エビチリ、麻婆豆腐などがある。
1959年、新潟市の甘味喫茶「みかづき」(当時の社名は「三日月」。)のオーナー経営者であった三日月晴三氏が考案したとされる。当時、この新しかったファストフードは1960年からみかづきのメニューに加えられ、地元で普及し始めた。今では新潟のソウルフードになっている。
現在では、小国製麺が家庭でも楽しめる冷凍のイタリアンを開発、販売している。
8.「栃尾の油揚げ(あぶらげ)」

栃尾の油揚げ(あぶらげ)
上杉謙信が幼少期を過ごした場所として知られる栃尾市の名物「油揚げ(あぶらげ)」。その特徴は、大きさで、通常の大きさの3倍はある。
栃尾市民だけでなく、新潟市民の私も居酒屋で、日本酒などとの相性の良さもあって、あぶらげをしょっちゅうオーダーする。ネギがのったあぶらげに醤油をかけて食べることもあれば、間に納豆が挟まったあぶらげを注文することもある。
ただ、一口にあぶらげと言っても食感は様々で、食べごたえをウリにするあぶらげもあれば、ふんわりした口当たりのよさが人気のあぶらげもある。栃尾観光協会のホームページには、「あぶらげ店マップ」が掲載されているほどだ。
このうち、「毘沙門堂本舗(びしゃもんどうほんぽ)」の油揚げは、マツコ・デラックスさんがテレビ番組の中で絶賛したほど。毘沙門堂本舗のホームページによると、薄皮でずっしりしっとりと厚みを出す伝統製法で造っているそうだ。大豆の濃さにこだわり、極限まで圧縮することで、大豆本来の濃厚な旨味を凝縮し、食べ応えのある質感を実現している。
9.「笹団子」
新潟の食のお土産の定番といえば、笹団子。(月刊)にいがた経済新聞で毎月掲載している「表参道・新潟館ネスパス」の売上ランキング(月別)でも、笹団子(粒あん)、笹団子(こしあん)は必ずと言ってよいほど、上位にランクインしている。


笹団子
新潟の伝統商品で、多くの家庭でも作られていて、筆者も、幼少期時代に彼岸などに祖父母の家(農家)に遊びに行くと、山のように盛られた笹団子が出てきたものだ。
餡の入ったヨモギ団子を数枚のササの葉でくるみ、紐で両端を絞っている。新潟県では、バナナのように上半分だけを剥いた状態で食べていくのがポピュラーな食べ方だ。
笹には殺菌効果があることから、戦国時代に携行保存食として生まれたのがはじまりのようだ。上杉謙信の家臣が発明したという俗説もあるという。昭和39年の新潟国体開催に際して「新潟土産の和菓子」として売り出したところ、全国的な人気を得たという。
現在、笹団子を製造販売している業者は新潟県内におよそ100軒、新潟市内におよそ50軒ある。その一つである、田中屋本店(新潟市江南区)では新潟市内に11店舗展開し、様々な笹団子を販売している(同社HPより)。また新潟市中央区にある同社の「みなと工房」で、笹団子の実演販売や、笹団子の作り方講座なども行っているそうだ。