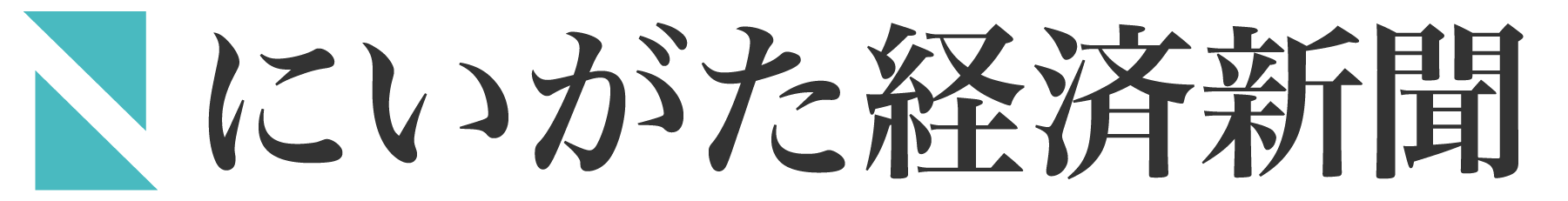住宅にも物価高騰の波、地場の大工・工務店の今後は─ 新潟県建築組合連合会インタビュー

一般社団法人新潟県建築組合連合会の会長を務める、アサツマ建築店の朝妻勝人氏
直近の注目記事をピックアップし、日曜日に再掲載します(編集部)
初回掲載:2025年2月20日(再掲載:3月2日)
木造住宅の人気は根強い。林野庁の調査によると、2023年の新設住宅着工戸数は82万戸で前年から4.6%減少したが、うち木造率は前年からほぼ横ばいの55%。一戸建て住宅に限ると木造率は91.4%と極めて高い。
木造の技術を伝えていくのに、地域の大工や工務店の存在は欠かせない。しかし、業界特有の課題や人手不足は慢性化しており、さらに近年は資材費、人件費、エネルギー費などコストの急激な高騰が追い打ちをかけている。
今回は木造建築の良さを入口に、地場の大工や工務店の現状、そして今後について、一般社団法人新潟県建築組合連合会に聞いた。

新潟県建築組合連合会が所在する新潟県建築国保会館(新潟市中央区)
住宅建築において、木造のメリットは多い。県内の大工や工務店など建築関係者が所属する県建築組合連合会のwebサイトでも「木造住宅のよさ」と題して発信。「木材が呼吸していると古来から言われているように、湿気の多い時は吸湿し、乾燥時には水分を発散させる機能を有し、居住性の高い健康的な環境作りをする」(同サイトから抜粋)と木の湿度調整を挙げる。
同連合会会長を務めるアサツマ建築店の朝妻勝人氏によると、さらに「リフォームのしやすさ」も木造建築住宅の特徴であるという。「家の間取りを容易に変えられるところは、木ならでは。木造だからこそ、例えば『ここの柱を抜いてしまおう』ということもできる」。
なお、大手ハウスメーカーは家を規格化し、工場でパーツを生産することも多いため、部屋単位でのリフォームに対応しづらい点もポイント。朝妻氏も「『家に和室が欲しいと思ったが、ハウスメーカーにはできないと断られた』という相談を受け、対応したこともある」と話す。設計の自由度を高めたい場合や、将来リフォームを検討する場合は地元の工務店に家造りを頼むことが賢明だろう。
木造は、鉄筋コンクリートや鉄骨に比べてコストを抑えやすいやすいことが度々指摘される。しかし、あらゆるコスト高によって住宅業界も値上げが続いているのが現状だ。一方で朝妻氏によると「法的な縛り」も値上げの要因になっているという。耐震基準や環境保全の視点など、建築に求められる基準は年々高度化しており、それが価格に反映されているかたちだ。「住宅の坪単価は年々上がってきている。これから先、新築住宅をつくれるのは一部の富裕層だけで、一般的な会社員は中古住宅を選ぶか、マンションか……という状況が来るのではないか」。朝妻氏には、そんな危惧すらあるという。

大工の現状について語る朝妻氏
一方で地域の大工や工務店も、こうした高騰のあおりを受ける。
2025年、県建築組合連合会は建築大工標準賃金を2万7,000円(税抜)に定めた。しかし現実は、「今、大工の年収は300万円程度。実際には、一日2万円貰っている大工なんていない。しかも、そこから大工道具や移動費など経費を引くかたちになる」(朝妻氏)。そのため、大手ハウスメーカーの手間請け(下請け)で稼いでいる大工も多い。
しかし標準賃金は、県や市町村の公共工事の労務単価にも反映される。そのため、多少強気でも上げていくことが重要だ。「標準賃金に満たない請求でも(消費者からは)高いと言われてしまう。その認識を変えてもらえるように、こちらからも発信していかなければいけない」と朝妻氏は課題感を強める。
また合わせて、前述した年々高度化していく法規制に対応しきれない点も、一人親方の大工や中小の工務店へのしかかっている。そのため県建築組合連合会では、そうした講習会も定期的に開催しているという。
住宅の高騰や人材不足……業界が苦しさを増す中、地方の工務店が進むべきはどこか。朝妻氏は「むしろ、木造建築へ携わる職人はこれから需要が大きくなる」可能性を指摘する。「住宅の価格が上がり、新築住宅が作れなくなるのであれば、中古住宅の需要が高まる。しかし、不具合のあるところはリフォームしなければならない。そこで、地場の大工が必要になってくるのではないか」(朝妻氏)。
地域における工務店や大工の存在は大きい。技術の伝承はもちろん、地域住民にとっては、大手メーカーよりも相談しやすい身近な存在として重要だ。今後も、地域に寄り添う彼らに注目していきたい。
【関連リンク】
新潟県建築組合連合会 webサイト