【独自取材】「処方箋なしで医薬品が買える」薬局が医学界と厚労省から受ける、理不尽な「迫害」の行方
新潟発「薬の零売」というビジネスモデル
「処方箋なしで病院の薬が買える」
そんな看板が掲げられている薬局が、新潟市中央区米山にある。薬剤師の荒居英郎さんが2001年に開業した「薬局アットマーク」。
看板の通り、抗がん剤、注射剤、抗精神薬、抗生物質の飲み薬など法律で「処方せん医薬品」に指定されているもの以外の医薬品、風邪薬や胃薬、湿布薬などを医師の処方せんなしで販売している。ここで薬を買う人は、ちゃんと薬局の趣旨を理解し、納得したうえで購入している。そのため薬を買うには会費500円を払って会員になる必要がある。それを差し引いても、使う側にとっては非常に重宝する薬局である。

新潟市米山の薬局アットマーク。病院にいかなくても病院の薬が買える薬局
多くの人は「医療用医薬品」というのは、しかるべき医師から出される処方箋によらない限り、提供されないと思っているのではないか。それは一部正しく、一部間違いだ。現行の医薬品医療機器等法(以下薬機法)では、処方箋を必要とする「処方箋薬」は、医療用医薬品全体のおよそ3分の2でしかないのだという。残りの3分の1(約7,000品目が該当する)は「非処方箋薬」なのだという。法律に縛られない「非処方箋薬」の中には、風邪薬や解熱鎮痛剤、点眼薬、湿布薬、漢方薬など数多くが含まれている。これらは薬剤師がいて、対面で販売されるなら処方箋なしで売っても良い薬なのだ。
処方箋なしで医療用医薬品を売る商法「零売(れいばい)」は、1889年(明治22)に薬品営業並薬品取扱規則が施行された時に既に存在したとされ、1960年に薬事法が施行された時点では全体の約7割が「要支持医薬品以外の医薬品」とされ、主に薬剤師会の役員や会員が経営する個人薬局で「こっそり」売られていたのだという。ある種の立場の者だけが有する特権のように「零売」は行われてきた。
法律の「抜け道」がそこにあったということだ。「抜け道」ではあるが「もぐり」ではない。2001年当時の荒居さんは、ここに着目し、日本で初めて「零売」を主たる業務とする薬局を開局した。非常に画期的な事象だった。
健康保険が適用されない「零売」は、一般的な処方箋薬局より割高な場合も当然ある。一方で薬局で売られる一般用医薬品(OTC薬)よりは割安なケースが多い。
なにより人々にとって「病院に行かなくても良い」メリットは計り知れないと思わないだろうか。診察費用がかからないというのはもちろん。病院にかかれば、院内感染におびえながら順番が来るまで長い時間待たされ、ようやく診てもらったと思ったら、たいした処置もなく「今日はお薬出しておきますから」というケースも少なくない。正直「風邪ぐすり」や「湿布」を入手するためにこんな想いはしたくない、というのが多くの意見ではなかろうか。少し前までのコロナ禍などは、まさに病院に行きたくなかったし、病院側も人を入れたくなかったという状況だったはずだ。
なかには、どうしても医者に手を握ってもらいながら「大丈夫だよ、薬出しておくからね」と言われてはじめて安心する高齢者もいる。そうした人たちの「社交場」としてあり続ける病院も存在する。そうした中で、ご存じの通り国の医療費は膨張を続ける一方。先の総選挙の際、新潟入りした日本維新の会の吉村洋文大阪府知事は「膨らむ医療費の、せめて10分の1でも教育に回してもらえば、全国の国立大学無償化も実現できる」と訴えていた。
聞いていて薬局アットマークのことを思い出した。薬の零売が社会に定着したならば、医療費の10%程度が削られるのではないか、と。
「処方箋なしに医薬品を売るのは危険なのではないか」という意見も当然ある。ただ法律で「処方箋なしで良い」と定められていて、病院や調剤薬局でも同じものを売る、それが危険だという理屈は果たして通るだろうか。「どうしても信用できない」という人は、混雑した病院で順番待ちをして薬をもらってくれば良いだけだし、それくらい利用者に選択の余地があっても良いのではないか。
薬局アットマークでは、丁寧な服薬指導をするし、会員制の採用によって売る側と使う側の「暗黙の了解」が担保される。安心か安心じゃないかは個人の判断だし、安全か安全じゃないかと問われればそれは法の範囲で言えば「安全」なのである。
現在、処方箋なしで医薬品を売る薬局は、全国に100ほどある。新潟で生まれた画期的なビジネスモデルは、2015年ごろに東京都三鷹市に「オオギ薬局」が開局したあたりから増え始めた。2019年に株式会社GOOD AIDが零売薬局の東京都内でチェーン展開をはじめ、同社の代表が「日本零売薬局協会」(2024年に解散)を設立した頃に、当局や医師会からバッシングが苛烈化してきた。
新潟では薬局アットマーク1店のみ。同店の系列も2号店もない。荒居さんに「2号店を出す気はなかったのか?」と聞くと「あまり目立ちたくないから、その気は一切なかった」と言う。零売の形態が「あくまで抜け道である」ことは否定しない。
そう、平成―令和の零売薬局の歩みは、医学界、薬剤師界、厚労省などから睨まれ、迫害される歴史の繰り返しだったのだ。
国会でも議論の的に
法律を逆手にとって利得する(実際はそれほど儲からないという)ところあれば、法律の庇護で既得権益にあずかる立場もある。そういう立場にとって、零売の存在は面白くない。例えばドラッグストアなど「正規ルート」の業界は、当然面白くないはずだ。また「特権」を侵された薬剤師界も面白くないだろう。病院離れにつながる存在なのは確かで、医学界も当然憤懣を持つ。そしてそれらを統括する厚生労働省も。
荒居さんが新潟に零売薬局を開業した直後の2002年、日本医師会が厚労省の薬事法改正案に「医薬品の分類見直し」の追加(医療用医薬品は消毒薬等を除きすべて医師等の処分や支持が必要な「処方箋医薬品」に変更するという内容)を迫り、これが採用され、参議院で可決された。事実上の「零売つぶし」だが、衆議院厚生労働委員会でこれに待ったがかかる。改正薬事法での分類見直しの背景に関係団体からの働き掛けがあったことが指摘され、問題とされたのだ。結果、改正薬事法では医療用医薬品全体の約6割を「処方箋医薬品」とし、それ以外を事実上の「零売可能」と位置付けられたのだ。
新潟で生まれた「国の医療費削減のカギを握るかもしれない」新しいビジネスモデル、たった1軒の薬局の存在が、国会を大いに揺るがしたのだった。
2005年には改正薬事法施行となったが、このタイミングで厚労省通知「処方せん医薬品の取り扱いについて」が発出され、その中には「天災などのやむを得ない場合を除き、それ以外の医薬品を処方せん調剤以外の方法で販売してはならない」とあった。一方で通知はあくまで法規制の効力はなく、零売薬局のスタイルは全国に伝播していった。
2014年には現行の薬機法施行となったが、当然、零売に関する条文はほぼ変更なし。厚労省では2005年と同じ内容の通知「薬局医薬品の取り扱いについて」を出してけん制する以上はできなかった。
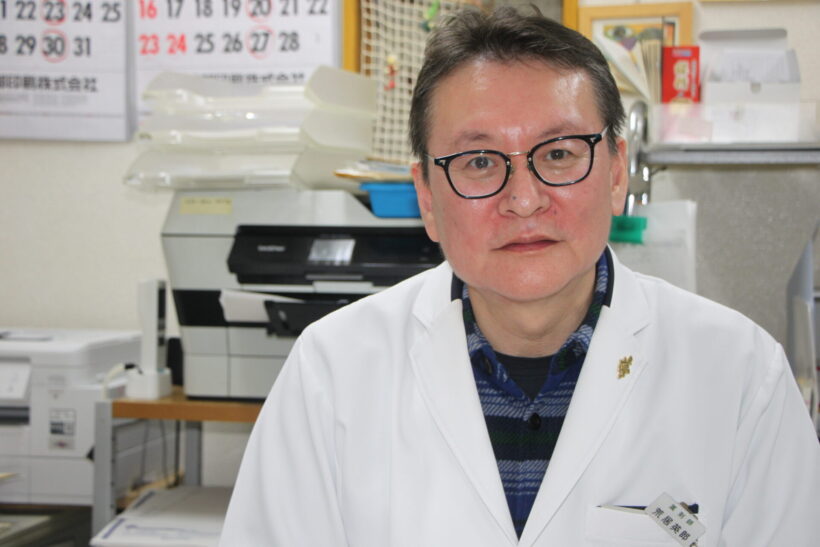
2001年、日本で初めて「零売」の薬局を立ち上げた荒居英郎さん
ついに法規制で締め出しか
2021年、日本眼科医師会が、零売薬局でステロイド点眼剤が販売されていることを問題視し、自民党を中心とした国会議員や厚労省などに対し声を上げ始めた。医師会と自民党の関係性については、巷間言われるとおりである。厚労省もこの動きに沿って、2023年2月に日本医師会や薬剤師会の役員、有識者で構成された「医薬品の販売制度に関する検討委員会」を立ち上げ、医薬品の分類見直し(実質の零売つぶし)を議論することとなった。
そして2024年、同検討会が取りまとめ案を作成し、これまで「厚労省通知」とされてきた零売規制案とほぼ同じ内容を改正薬機法案として提出することを決定した。「零売憎し」とする既得権益にあずかる面々で構成された会によって法案は揉まれた。
このまま法案が国会を通過すれば、零売薬局は「非処方せん薬品」を売ることができなくなり、その業態自体が消滅する。
この動きを受け、2025年1月17日には零売薬局を運営する3者が原告となり、「零売の法的規制は憲法第22条の職業選択の自由の侵害である」という趣旨の地位確認等請求訴訟を起こした。ここまで「零売つぶし」は粛々と進められており、手をこまねいていては多くの国民が注目しない中で国会を通過してしまう可能性が高い。大衆の目を引くためにも、せめてもの問題提起をしたい気持ちは理解できる。
零売側にとって、旗色は決して良くない。1月27日に開かれた自民党厚生労働部会では、法案がすんなり通過したという(ある種、予想通りだ)。法案の概要欄には医薬品の分類見直しなどについて一切触れられていないが、中身を見ると医療用医薬品について「処方箋に基づく販売を原則とし、やむを得ない場合にのみ薬局での販売を認める」と謳われている。これはかつての厚労省通知とほぼ同じ内容。
「岩盤」というものはこのように形成されていくのか、というのをまざまざと見せつけられた思いだ。
(文・写真 伊藤 直樹)


