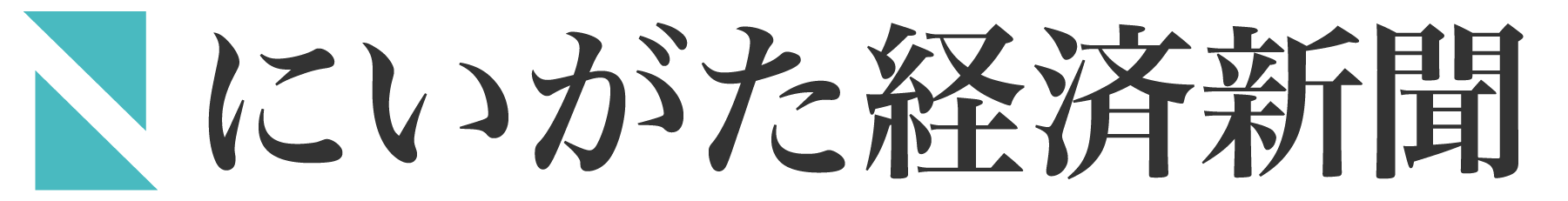【オリジナル企画】もし新紙幣を新潟の偉人で選んだら果たしてどうなるのか?をやってみた
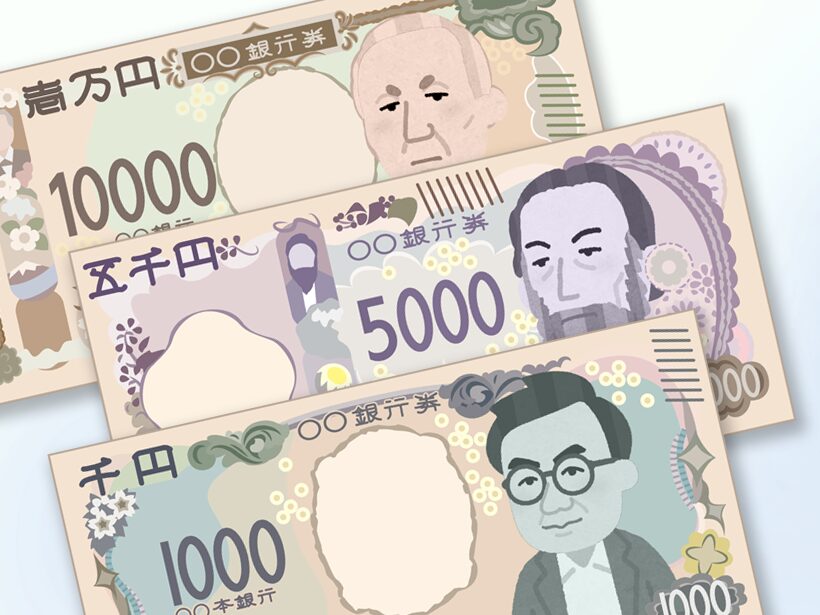
(画像はイメージです)
昨年の7月からなんと20年ぶりの新紙幣に変わったわけだが、昨年末くらいから流石に財布の中にも新札が入っているようになった。にいがた経済新聞でも特集記事にしているが、この度、「新紙幣を新潟の偉人で選んだらどうなるか?」という企画を思いつき、実行してみた。この企画はいずれ正夢になる?
まずは、千円札に選ばれた坂口安吾(1906年〜1955年)。安吾は新潟市出身の小説家・評論家だが、戦後文学を代表する作家の一人であり、太宰治、檀一雄らとともに「無頼派」と呼ばれる。安吾の圧倒的な代表作、「堕落論」は全国的な知名度があり、文芸分野での新潟県出身の偉人といえよう。

東洋大学印度哲学倫理学科へ進学し、文学の道を志す。戦後の混乱期に「堕落論」を発表し、「人間は堕落することで生きる」とする独自の人生観を示した。彼の作品は社会の虚飾を暴き、人間の本質に鋭く迫るものが多い。
代表作には「白痴」「桜の森の満開の下」などがある。破滅的な生き方をしながらも、誠実に文学と向き合い続けた生涯を送った。
次に、五千円札の小林虎三郎(1828年〜1877年)である。

幕末から明治にかけて活躍した教育者・藩士であり、新潟県長岡市(旧長岡藩)出身。彼の名を広く知らしめたのが「米百俵」の精神である。戊辰戦争で敗北し困窮する長岡藩に送られた百俵の米を、藩士や民衆に配るのではなく、売却して教育資金とし、国を担う人材を育てることを決断した。
この理念は、後に明治政府での教育政策にも影響を与えた。虎三郎は長岡藩の藩校・崇徳館の再興に尽力し、優れた教育者として後進の指導に力を注いだ。彼の信念は、今日に至るまで「教育こそが国家の礎である」という考え方として語り継がれている。
2002年5月に小泉内閣が発足し、当時の小泉純一郎首相が最初の所信表明演説の結びで「米百票の精神」を引用したことで、一気に虎三郎の知名度が全国的に広まった。
最後に、一万円札の前島密(1835年〜1919年)だ。「日本郵便の父」として、現在の1円切手にもなっているほか、大隈重信とも親密で、前島は早稲田大学の学長も務めている。

新潟県上越市(旧越後国頸城郡)出身の官僚・実業家・政治家であり、日本の郵便制度の創設者として知られる。幕末には蘭学を学び、江戸幕府の外国事務局で通訳などを務める。明治維新後、近代化を進める政府に参画し、日本に郵便制度を導入。
1871年に全国的な郵便制度を確立し、近代的な通信の基礎を築いた。また、郵便制度以外にも鉄道・電信の普及、貨幣制度の改革などに尽力し、日本のインフラ発展に貢献した。さらに、漢字の簡略化や言文一致運動を推進するなど、教育・言語改革にも関心を持ち、その影響は現代の日本語表記にも及んでいる。
新潟出身ではいまだかつて紙幣のモデルになった人はいない。いつか、わが新潟県からも選ばれるように活躍する人が出てきてくれることを期待している。