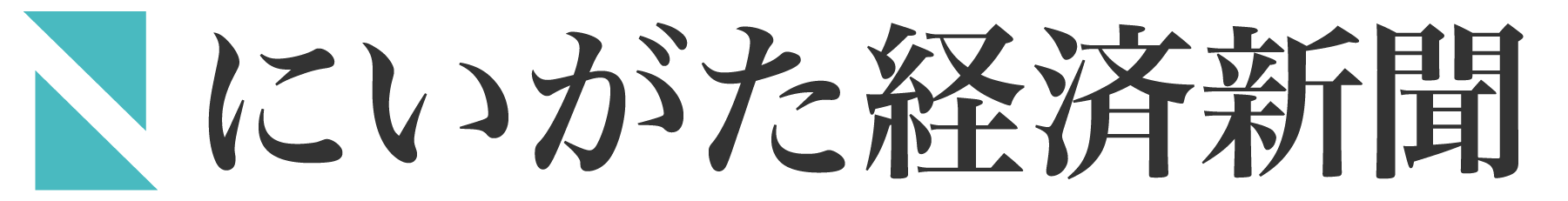海と空を舞台に、日本海の安全を守る第九管区海上保安本部の活動に迫る

「海上保安庁」と聞くと、どんなイメージが浮かぶだろうか。その活動領域は、海の警備や海難救助だけに留まらず、震災時に陸送できないものを海上から搬送したり、時には空からもその機動力を発揮するなど、さまざまな形で人々の暮らしを守る活動を展開している。

海上保安庁は、1948年5月1日、米国沿岸警備隊を参考に、海上の安全や治安の維持に関する行政的に一元的かつ横断的に実施する海上保安機関として設置された。毎年5月12日は「海上保安の日」。
海から、空から。海の警察・消防を担う海上保安庁
「海上保安庁は、国土交通省の外局で、主に海における警察・消防の役割をしています。海上自衛隊と間違えられることがこれまで多かったですが、だいぶ認知度も上がってきたでしょうか」と教えてくれたのは、第九管区海上保安本部(新潟市中央区)の広報・地域連携室室長で総務課専門官の加島宏輔さん。

第九管区海上保安本部広報・地域連携室で総務課専門官の加島宏輔さん(写真右)と、総務課危機管理係の本間善光さん(写真左)
まずは海上保安庁の業務全般について迫ってみることにしよう。
海上保安庁の業務は主に①領海警備、②治安の確保、③海難救助、④海上防災、⑤海海洋調査、⑥海上交通、⑦海洋環境の保全、⑧国際連携協力の、大きく8つの種類に分けることができる。

具体的には、海上で違法行為を行う船舶等がいないかパトロールをしたり、プレジャーボートで遊んでいる最中に溺れてしまった時のレスキュー、航行不能になった船舶や乗組員の救命救助など、さまざまな場面で海上保安庁の活躍によって暮らしや生命は守られている。
記憶に新しいところだと、2022年の知床遊覧船事故の救助や2023年の今治沖日本籍貨物船衝突・沈没事故なども、対応を海上保安庁が行った。
「海上保安庁というと船に乗っているイメージがあると思いますが、航空機のパイロットもいますし、陸で仕事をしている職員も全体の約5割を占めます」(広報・地域連携室で総務課危機管理係の本間善光さん)

船が衝突せずに安全でスムーズな運航ができるよう情報提供を行う 、海上交通センター管制運用官
2024年元旦に発生した能登半島地震の際は、物資の陸送が難しかったため海上保安庁が海上から水を届け、約2ヶ月間活動し合計7,888.5トンの水を被災地へ届けた。


能登半島地震時の対応の様子。巡視船による給水支援だけでなく、災害状況の調査救急患者等の搬送、支援物資輸送など、多方面で活躍した。
“海猿”も所属。海に関わる多彩な専門職集団。
海上保安庁の巡視船には、一隻の船の中にも統括する船長、操船を行う航海科職員、通信を行う通信科職員、ヘリコプターを操縦する航空科職員など、専門性の高い技術を持つ職員が多数乗船している。

「巡視船には安全確認をしながら船を運航する行う航海士もいますが。これが漫画『ワンピース』でいうところのナミですね」(加島さん)
さらに緊急時には特殊救難隊や潜水士、機動救難士など人命救助の専門部隊も出動。特に潜水士に関しては、漫画やテレビドラマ、映画でヒットした「海猿」で一躍その存在がお茶の間に広まり、認知されるようになった。

北朝鮮漁船に放水する巡視船。海上保安庁の現場勢力は、2025年4月現在、船艇が476隻、航空機98機(無操縦者航空機含む)、航路標識5108基を保有している。
日本海を24時間365日守る第九管区海上保安本部
海上保安庁では、全国を11の管区に分けて各海上保安本部がそれぞれの管轄エリアを守っており、新潟県民の生活を守ってくれているのが、第九管区海上保安本部だ。 新潟県・富山県・石川県沿いの日本海を担当している。
このエリアは特に、外国漁船による違法操業や、北朝鮮による弾道ミサイル発射の際の調査や注意喚起、木造船などの漂流・漂着などが多い傾向にある。また好漁場があるので、領海・排他的経済水域(EEZ)における対応で、しっかり日本漁船の安全確保を担うことも重要なミッションの一つになっている。

海上自衛隊の金曜カレーならぬ、海上保安庁では入港カレーといって、入港日のメニューがカレーやハヤシライスになることが多いそう。
近年第九管区海上保安本部が実際に出動した災害や事故としては、前出の能登半島地震の他にも、例えば直江津港沖で故障したプレジャーボートに乗っていた釣り人の救助や、今年に入ってからは東京税関新潟税関支署と関東信越厚生局麻薬取締部、新潟県警と合・共同捜査による海上貨物を利用した覚醒剤の密輸の検挙などが挙げられる。
「毎年少なからず海難事故は発生していますし、近年は、能登半島地震に限らず、震災や豪雨などの自然災害への対応が増えているように感じます」(加島さん)
新潟県内には第九管区海上保安本部と新潟海上保安部、新潟航空基地、2つの保安署があり、日夜日本海の安全を守っている。
新潟海上保安部には巡視船が5隻、さらに上越海上保安署と佐渡海上保安署にも1隻ずつ、さらに新潟航空基地には飛行機・ヘリコプター合わせて5機が配備されている。近年は巡視船「えちご」が事故から復帰したこともあり、より一層の活躍に期待が寄せられている。

新潟海上保安部の巡視船「さど」。

佐渡市出身の本間さん。現職の前は航海科職員として巡視船「さど」に乗船していた。「祖父が漁師で、海で生活をしている人を守る仕事がしたいと海上保安官になりました」
海上でのトラブルは迅速に「118番」へ
いざ、海難事故を目撃したり当事者になった場合、どうしたら海上保安庁にレスキューを求められるのか。もしもの時に助けを求める先が「118番」だ。警察の110番、消防の119番と同じで、この番号に電話をかけると最寄りの管区本部につながる。
これに加えて、新たに2025年1月18日から始まったサービスが、スマートフォンのカメラ機能を使った「Live118」だ。
「118番の通報者の方にご了承いただけた場合、Live118につながるショートメッセージを送付します。ショートメッセージからサービスに繋ぐと通報者の方のスマホのカメラを通して現場の状況を正確に把握し、適切な対応を案内できるようになるんです」(加島さん)
開始からわずか約1ヶ月だが、すでに有効活用された事例もあり、今後の浸透・活用が望まれる。
「平和な日常」のそばに海のプロフェッショナルの活躍あり
私たちの穏やかな日常は、その裏に海上保安庁の絶え間ない活動があるわけだが、その現場が洋上であったり有事の場合などで、なかなか普段海上保安庁の活動を目にすることは難しい。
そこで海上保安庁の活動の一端に触れたり交流を持てる場が、イベントや「海上保安友の会」という会だ。
海上保安友の会はファンクラブ的な組織で、海上保安庁が行う行事の見学案内があったり、定期情報誌の送付を受けることができる。


“安心安全を享受できる日常”の根幹を支えてくれている海上保安庁。安全な日常を維持するためには、私たちも常日頃の安全への意識は大切だ。
加島さんも「海で遊ぶ際の自己の安全確保はしっかり行なっていただきたいです。それでも万が一海で事件事故が起こったら、すぐに118番に通報してください」と呼びかける。
海で楽しく遊べるのも、おいしい近海の魚を食べられるのも、穏やかな暮らしも、そのそばには海上保安官たちの24時間365日体制の働きがある。
改めて地域への貢献に敬意を払うとともに、その活躍に注目したい。