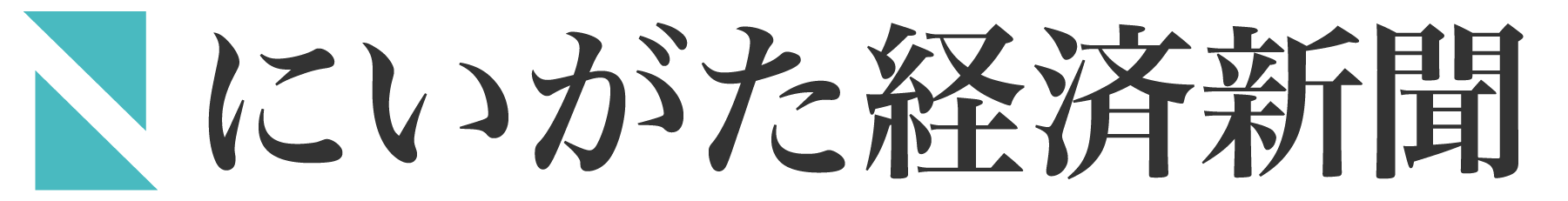「下流社会」著者の社会デザイン研究者三浦展氏が凱旋講演、「個人経営の店や地産地消の店舗を」

新潟県上越市出身の三浦展氏
社会デザイン研究者の三浦展氏は、消費社会や家族、都市の変化を研究し、新たな社会のあり方を提案してきた。1958年に新潟県糸魚川市で生まれ、新潟県上越市高田で育つ。1982年に一橋大学社会学部を卒業後、パルコに入社し、マーケティング情報誌「アクロス」の編集に携わる。その後、三菱総合研究所を経て、1999年に「カルチャースタディーズ研究所」を設立した。
三浦氏は、ベストセラーとなった「下流社会」をはじめ、「第四の消費」「家族と幸福の戦後史」「ファスト風土化する日本」などを著し、現代社会の問題を鋭く分析してきた。このほど、出身地の上越市のたてよこ書店で講演を行った。
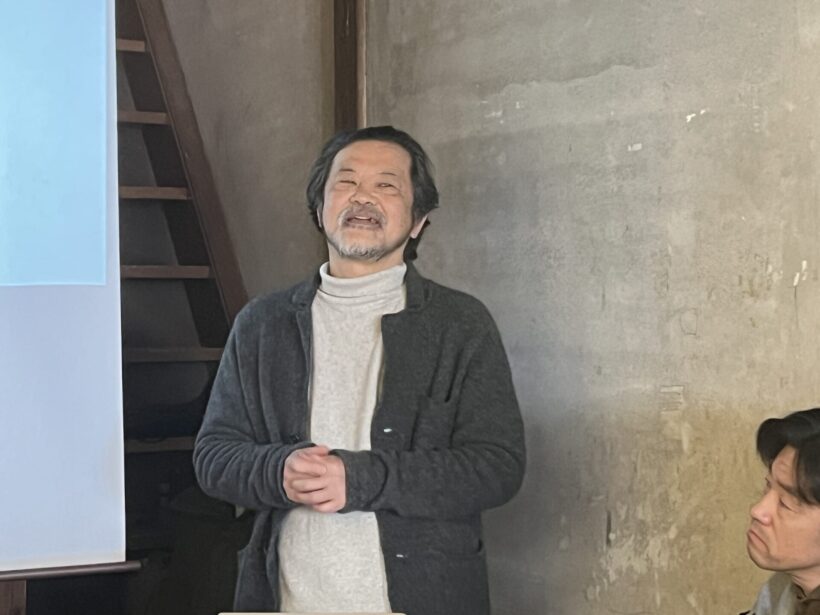
地元に凱旋講演した三浦展氏
三浦氏の研究の一つに、「ファスト風土化」という概念がある。これは、大規模チェーン店やショッピングモールの進出により、地域の独自文化が失われ、均質的な都市景観が広がる現象を指す。
この現象が進むことで、地域コミュニティの希薄化や、住民同士の交流の減少が懸念されている。特に、子どもたちの遊びが一人で完結する傾向が強まり、社会性の発達に悪影響を及ぼす可能性がある。また、健康格差の拡大や精神的な発達の阻害も指摘されている。
経済面では、地元企業の正社員雇用が減少し、非正規雇用の増加による所得の低迷や結婚の困難化が問題視されている。さらに、地域社会の流動化や匿名化が進み、治安の悪化につながる可能性もある。
こうした問題への対策として、三浦氏は都市の拡大を抑制し、住宅と商業施設を近接させ、個人経営の店舗を増やすことで、徒歩で移動できる魅力的な街を形成することが重要だと指摘している。また、多様な経済階層の人々が共存できる住宅の整備や、歴史的街並みの保存も求められる。
三浦氏は「全国チェーン店への依存を減らし、地域経済を活性化させるために、個人経営の店や地産地消の店舗の増加が推奨される。地域の魅力を活かした持続可能な街づくりが、日本の都市にとって今後の課題となる」などと話した。

新潟県上越市の雁木通りの一角にある「たてよこ書店」
【関連記事】
【三浦展氏のにいがた経済新聞での過去の連載記事】
(文・撮影 梅川康輝)