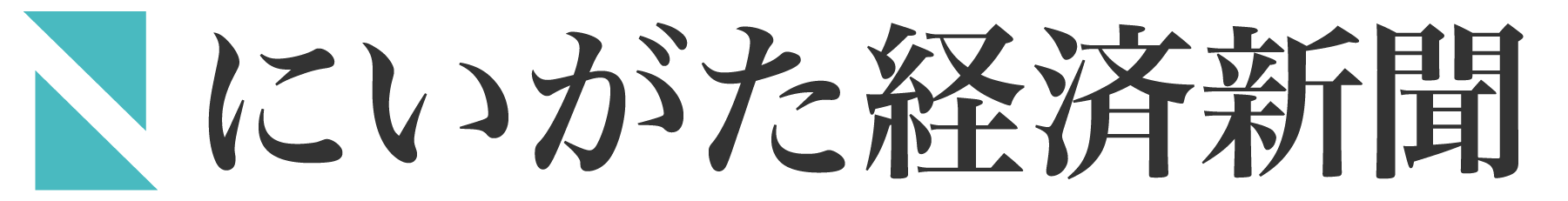新潟県知事に原子力発電所事故による避難生活への影響についての検証結果を報告
新潟県原子力発電所事故による健康と生活への影響に関する検証委員会の松井克浩副委員長が12日、福島第一原子力発電所事故による避難生活への影響に関する検証の取りまとめを花角英世新潟県知事へ報告した。
新潟県では、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に関する議論を始める前提として福島事故の徹底的な検証を行うことになり、その一環として2017年に福島第一原発事故による「健康と生活への影響に関する検証委員会」がスタートしたという。検証委員会による検証結果の主な結論は以下の通り。
◎避難区域内・外の違いはあり、生活再建を進めた人も少なくないが、依然として生活再建の目処が立たない人もいる。長引く避難生活に加え、様々な「喪失」や「分断」が生じており、震災前の社会生活や人間関係などを取り戻すことは容易ではない。
◎避難者は、仕事や生きがい、人間関係の喪失などの点で多くの犠牲を払っている。しかし、各世帯はそれぞれ合理的な決断の結果として避難行動をとったのであり、その選択を十分に理解することが必要である。
◎避難していない場合でも、放射能による健康被害への不安がリスク対処行動をもたらし、生活の質を低下させている。
◎区域内避難者でも、依然として生活再建や地域再建について見通しが立てられず、不安を感じている人が少なくない。また、避難元地域から切り離された「ふるさとの喪失/剥奪」は深刻な被害をもたらしている。
◎広域避難が発生すると、避難元の属性や避難先の自治体間における支援策の違いなどにより、支援対象から外れてしまう人たちが生まれる。
◎時間の経過とともに避難者に対する理解が薄れており、避難者が抱える問題や困難が見えにくくなっている。周囲からの誤解や偏見、差別もみられる。
◎避難者ごとに課題が個別化・複雑化する中で、生活を取り戻すための長期の支援が必要とされる。また、賠償や復興施策の改善を求めて、被災当事者による集団訴訟などの取組も進行中である。
松井副委員長は、「新潟県内でも依然として2,000人を超える人々が避難生活を続けている。新潟県民の皆様にも、ひとたび原発事故が起こると、その周辺の住民の生活がどのような影響を受けるのかについてぜひ"自分ごと"として考えていただきたい」と話した。
また、報告を受けた花角県知事は「検証の結果・内容について県民の皆様にも情報共有、ご理解いただけるような機会を作り、原発の稼働問題についての議論の判断資料とさせていただきたい。我々行政もこういった問題にどういう形で関わり、取り組むか検討していく」と話した。
2011年3月の東京電力福島第一原発事故によって深刻な放射能汚染が広がり、避難指示が出された区域の内外から多くの住民が避難を強いられた。復興庁のデータによると、福島県の避難者数は2012年のピーク時に約16万5千人を数えており、避難を選択しなかった住民も不自由な生活を送ることになった。
一方、新潟県には、今回の健康と生活への影響に関する検証委員会を含めて検証作業を行う3つの委員会と、検証総括委員会があり、昨年には、新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会が、福島第一原発事故の検証報告書を花角知事に提出している。