新潟ゆかりの文学者たち(5) 相馬御風「小川未明論」(1971年12月角川書店刊『近代文学評論大系』第4巻所収) 片岡豊
糸魚川駅日本海口を出ると、駅前広場の右手に立派な文学碑が眼に入ります。その碑には「ふるさとの山はなつかし/ふるさとの川はなつかし/疲れたるこころいだきて/足おもくかへり来たれば/ふるさとに山はありけり/ふるさとに川はありけり」と始まる三連の詩が刻まれています。これは糸魚川が生んだ文学者、相馬御風の「ふるさと――或復員者に代りて――」と題された御風最晩年の作品です。二連で父母との再会、三連で友とふるさとの土との再会を詠っています。いまこのときも戦争や災厄で「ふるさと」を離れざるを得ない人びとが世界各地にいることを思えば、ひときわ身に染み入ってきます。
相馬御風、その名を聞いたことはあるような、という方が多いかも知れません。でも、早稲田大学の校歌「都の西北」の作詞者だと聞けば、そういえば我が校の校歌の作詞者じゃなかったかなと思い出す人もあるでしょう。彼は新潟県内のみならず、全国北から南まで215校に及ぶ校歌を書いているのです。歌といえば、我が国初のヒット歌謡曲「カチューシャの唄」も御風の作詞。これは1914(大正3)年、島村抱月の芸術座がトルストイの「復活」を上演したときの挿入歌で中山晋平の作曲。主演の松井須磨子が歌って大評判となりました。あるいは、若い人たちでも多分知っているだろう童謡「春よ来い」もまた御風の作詞、曲は弘田龍太郎です。
1883(明治16)年7月10日、糸魚川の代々寺社建築の棟梁の家に長男として生れた御風(本名昌治)は旧制高田中学に進み、一歳年長の小川未明と同じ学び舎で過ごしました。この頃から歌作を始め、当時歌壇の中心であった新詩社、竹柏会に関わって歌人として出発します。東京専門学校(早稲田大学)予科から英文科に進み、在学中の1905(明治38)年に歌集『睡蓮』を東京純文社から自費出版。卒業後は早稲田文学社に入り、島村抱月によって復刊された『早稲田文学』の編集に当たりました。また三木露風や野口雨情らと「早稲田詩社」を起こして詩人としても活動します。折しも文壇は自然主義文学全盛期を迎えようとしている頃で、御風は詩壇に口語自由詩を提唱。またツルゲーネフやゴーリキー、トルストイの翻訳を発表する一方で文芸評論にも健筆を奮い、1912(大正元)年9月には第一評論集『黎明期の文学』を新潮社から刊行して自他共に許す自然主義文学の論客として活躍しました。
しかしながら、「『黎明期の文学』を読んだ人は、相馬君が耐えず動揺してゐる人であるといふことを知るであらう」(「『黎明期の文学』合評」1912年12月『新潮』)と小川未明が評したように、御風は自ら自然主義文学を論ずる時のキーワード「主観」と「客観」との間に葛藤する人であったのです。御風はその後白樺派の文学に触れ、また大杉栄の『近代思想』に接するなかで「自我の発展」(「北村透谷私観」1908年『早稲田文学』)と外界とのありように対する葛藤を深めていきます。そして1916(大正5)年2月、春陽堂から『還元録』を刊行後、同年3月には「ふるさと」糸魚川に退いて文壇から離れることになったのでした。1950(昭和25)年5月8日に没するまでの後半生は、ふるさとの人びととともに歌作をつづけ、一方で良寛研究に没頭。また多くの随筆を書いて地域の文化人として生涯を終えたのです。
「私達の郷国の越後から出て来て、東京の文壇にたって居る創作家は、小川未明君の外にない。小川君と私とは中学校このかたの同窓の友達である」と書き起こされ、「わが文壇に於て真にロマンチシズム乃至はネオロマンチシズムの作家を求むれば、小川未明君の外に一人の顕著なる作家のない事を、私は断定して憚らぬ」と結論する「小川未明論」は、1912(明治45)年1月の『早稲田文学』に発表されました。雪国の風土を土台に、時の文学潮流に飲み込まれることなく「自分だけたゞ一人で、自分の道を歩いてきた」若き小川未明を論じて興味深い作家論です。やがて「日本のアンデルセン」と言われるようになる未明と、文壇の第一線を早く退いて故郷に隠棲した御風。二人の歩みの異なりを思えば、なお一層味わいのある作家論だと言っていいでしょう。
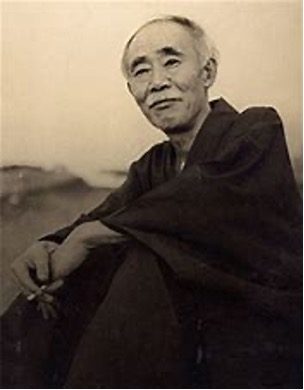
晩年の御風 相馬御風記念館HPより

糸魚川駅前の相馬御風文学碑

相馬御風居宅 糸魚川市大)町2-10-1(新潟県史跡)

片岡豊
元作新学院大学人間文化学部教授。日本近現代文学。1949年岐阜県生れ。新潟県立新津高校から立教大学文学部を経て、同大学院文学研究科博士課程満期退学。現在、新潟県上越市で「学びの場熟慮塾」主宰。


